�����ɂ����鎀���� �P
�@�E�E�E�����ɂ��������
�����́A�����̒a���A���̌n���A���̐��݂ɂ��đ��l�Ȍ`�Ń_�C�i�~�b�N�Ɍ���Ă���B�ȉ��A�����ł́A�l�Ԃ������邱�ƁA
�����Ď��ʂ��Ƃɂ��āA�����������Ȃ���߂����Ă���̂��ɂ��Č����Ă��������B
�����̑n�����P�̂P�Q�A�Q�P�A�Q�T�A�R�P�ɂ��A���������߂���l�́A�_�����t�ƃ��S�X�ɂ���Ė������ɌĂяo��
��ʂɑ������A�_���g������n�������������E�̒����F����錾�ɗ���������B���̂��Ƃ́A�����̃X�g�[���[�́A������
��^��ʂ��Ă��̖����J���Ă���Ɖ�����ׂ��ł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B
�R�[�w���X���X�|�S�ł́A�R�[�w���X���u������҂Ƃ��đI��Ă���҂ɂ͊�]������B�����錢�͎����鎂�q�ɗD��v�ƌ����Ă�
��B�܂��A�n���L�R�|�P�X�A�R�[�w���X���R�̂P�X�|�Q�O�ł́A�l�́A�u�o�������A�䂦�ɐo�ɋA��v�Ɠ`�����Ă���B�����Ȃ�l�Ԃ�
�����Ă������悤�Ɏ����}���A��O�Ȃ����̐������邱�ƂɂȂ�B�u���ƁA���҂����҂Ɠ��l�Ɏ��ʂ̂��v�i�R�[�w���X���P�U�j�ɂ���悤
�ɁA�u���v�Ƃ�����߂̑O�ł͒N�ɂƂ��Ă������Ȃ̂ł���(1)�B
�����[�����Ƃ̈�Ƃ��āA��������ɂ����鑼�̕����ɂ�����v�z�Ɣ�r����ƁA�����ł͐l�Ԃ̎���̐��Ɋւ��錩���Ɋ�
���Ă͋ɂ߂ď��ɓI���T���߂ȑԓx�������Ă���Ƃ������Ƃ��B
�Ⴆ�A�R�[�w���X���U�|�P�Q�ɂ����āu�l�ԂɁA���̈ꐶ�̌�ǂ��Ȃ�̂�����������̂͂ǂ��ɂ��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���@���A��������
�犮�S�ɓƗ����ĕʂ̐��E���`������Ƃ������Ƃ͂Ȃ������B�܂��A�����[�l�������\���͂�������(2)�A���n���F�ɑR����@���_
�i�ƂȂ邱�Ƃ͂Ȃ������̂ł���B
�A�K�y�A�푈�̎���ɂ����ẮA�`�l�̕s���̊ϔO�╜���v�z(3)���M�����Ƃ��ł��邪�A���̎���ɂ����Ă��A�����͐_��M����
���`�ɏ]���Đ���������Ƃ����M�̗i��Ƃ���������ꂽ�ϓ_���O��Ƃ��ēW�J���ꂽ�v�z�ł��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�����A���̎���̐l�X�̐M�����̎����I�ȋ�Ԃ́A�����݁A�����ɐ����Ă���u�Ԃ��ő���ɐ�����������Ƃ������ƂɎ���u��
�Ă����̂ł���B�����̐��������݁A�����Ă���Ƃ����m���Ȏ������^������p�������������ɂ����鎀���ςƉ����邱�Ƃ��ł�
��B
���āA��������́A�����ɂ����Ă͈�̔@���Ȃ鐶�����E���`����Ă���̂��ɂ��Č�������B���m�̔@���A�Ñ�ɂ����ẮA
�_�b�̐��E�ł͐_�X�̓����ɂ���Đ����̐��E���a�����Ă���B�Ƃ��낪�A����ɂ����Ă͂����ł͂Ȃ��A�u���n���F�_���y�̐o��
�`������l�̕@�ɖ��̑��𐁂����ꂽ�v�i�n���L�Q�[�V�j���Ƃɂ���Đl�Ԃ͐����鑶�݂ƂȂ����B����͌����܂ł��Ȃ��A����ɂ�����
�l�Ԃ̒a���Ƃ��̐����́A�_����^����ꂽ�����Ƃ��čl�����Ă���Ƃ������Ƃ��B
�l�Ԃ̒a���Ƃ��̐��������S�����́i��ΓI�ȁj���݂Ƃ��Ă̐_���畊�^����Ă���Ƃ������t���́A�\���L�R�Q�|�R�X�ɂ�����u����
���ɐ_�͂��Ȃ��B�����E���A�����������v�Ƃ��������ɂ���Ė����ł���B�����A�_�ɂ���ė^����ꂽ�����͐l�Ԃ����Ɨ�����
���L���ƂȂ�킯�ł͂Ȃ��B�_�ɂ���ė^����ꂽ�����͐_�ɂ���ĒD������̂ł���B�l�Ԃ��u��������Ă���v�Ƃ��������A��
��A�l�Ԃ̐����͐_����̎����ł���Ƃ������߂́A�܂��ɂ�������ǂݎ�邱�Ƃ��ł���̂�(4)�B
����ɂ����ẮA�l�Ԃ́u���v�Ɓu���v�̑o�����_�̎�ɂ���Ĉς˂��Ă���Ƃ����l�����́A�l�X������̐l���ɂ��Đ�]����
�ς���Ȃ��Ȃ������A���E���邱�Ƃ��ΓI�ɋ֎~������̂ł���B���i���S�|�R��u�L�U�|�X�Ȃǂɂ����ẮA�ɓx�̐�]������
����I�сA�����ؖ]����l�Ԃ́A��������f�Ƃ������Ƃ͂����A�_�ɑ��Ď����̖������グ�Ă����悤�ɒQ�肵�Ă���(5)�B�@�@
�����Ŗ����Ȃ��Ƃ́A����̐l�X�ɂ�����u���v�Ɓu���v�ɑ���ԓx�͋ɂ߂ĎI�ł���A�u���v�Ƃ͗^����ꂽ�����̉��Ő����邱
�Ƃł���A�u���v�Ƃ͗^����ꂽ������^�����_�����グ�邱�ƂȂ̂ł���i�T���G������Q�|�U�A���u�L�P�|�Q�P�j�B
�_�͐l�Ԃɐ�����^�����킯�ł��邪�A����͌��t�E���S�X����ė^�����̂ł������B�����A�_�͐l�X���j�����A�u�Y�߂�A������A
�n�ɖ�����B�܂��n���]�킹��B�C�̋��A�V�̒��A�n�����ׂĂ̐��������x�z����v�ƌ�����̂��i�n���L�P�|�Q�W�j�B����ɂ�����
�_�̑��݂͕s���s�ς̃C�f�B�A�I���݂ł͂Ȃ��A�_����l�Ԃɑ��Č�肩����u�l�Ԃ�T�����߂�_�v(God in search of man)���狿
���Ă�����̂ł���(6)�B
�@�@�u���́A�����A�V�ƒn���ؐl�Ƃ��ČĂяo���B�����āA���Ǝ����A�j���Ǝ��N�̑O�ɒu���B�N�͐���I�ׁv�i�\���L�R�O�|�P�X�j�B
�@�@�u�p���ɂ݂ɂĂł͂Ȃ��A���w���F�̌�����o�Â���̂ɂ���āA�l�͐�����v�i�\���L�W�|�R�j�B
�@�@�u�N�̐_�A���n���F�������A���̐��ɒ����]���A�ނɂ��]���Ȃ����B���ꂱ�����N�̐��Ȃ̂��v�i�R�O�|�Q�O�j�B
�����̌��t�ɂ́A�_����^����ꂽ�l�Ԃ̐l�����邱�Ƃ́A�����ɐ_�̌��t�E���S�X�����Ƃł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B
�܂�A�u�l�Ԃ��\���I�ɐ�����Ƃ������Ɓv�́A�u�I�ɐ_����̌��t�����Ɓv�Ɠ����ł���ƍl�����Ă����̂��B
����ɂ�����u���v�̑������͈ȏ�̍l�@�Ŗ��m�ɂȂ������A����A�u���v�ɑ���l�X�̑������͂����Ȃ���̂ł������̂��낤���B
����ɂ����Ắu���v�Ƃ́A�_���l�Ԃɓ��������A�l�Ԃ��_�ɉ�������Ƃ������݊W���I�����Ă��܂��Ƃ����Ӗ��𐬂����̂ł���B
�u���Ȃ������҂̂��߂Ɍ�Ƃ��s������A���삪�N���オ���Ă��Ȃ��Ɋ��ӂ�������肷��ł��傤���B��̒��ł��Ȃ��̎����݂��A
���Ȃ��̂܂��Ƃ̖łт̍��Ō��ꂽ�肷��ł��傤���B�ł̒��ł��Ȃ��̌�Ƃ��A���Ȃ��̌b�݂��Y�p�̒n�Œm��ꂽ�肷��ł���
�����v�i���тW�W�̂P�P�|�P�R�A�U�̂U�j�Ƃ�����肩�痝��������@���A�l�Ԃ́u���v�Ƃ́A�_����肩���Ă��Ă��A����ɑ��Č����ē���
�邱�Ƃ��ł��Ȃ��A�Ƃ������Ԃ��Ӗ����Ă���̂ł���(7)�B
���̂悤�ɂ��āA�����������ւ̏����̎������n�I�ɕ�܂��Ă���A���������s�\���Ƃ��Ē[�I�ɉ��߂���Ă��邱�Ƃ����m
�ɂȂ����B����ł́A���̂悤�Ȕw�i�̉��A�l�Ԃ̐��݂̍���͂����ɓW�J����Ă���̂��ɂ��čl���Ă݂����B
����̐����ɂ�����ے��I�ȕ\���Ƃ��ẮA�����A���A��i���тP�O�S�̂Q�X�|�R�O�j�A���i�n���L�Q�|�V�j�A���i���r�L�P�V�|�P�P�A�\���L
�P�Q�|�Q�R�j�Ȃǂ̕\��������B����́A����ɂ����鐶���́A�͂⊈���̏ے��Ƃ��čl�����Ă��邱�Ƃ�����������̂ł���A������
���ۓI�ȊϔO�ł͂Ȃ����Ƃ��킩��B�n���L�ɂ����ẮA���ݏo���ꂽ���́u�Y�߂�A������A�n�ɖ�����v�i�n���L�P�|�Q�W�j�ƌĂт�
�����Ă���A�l�́A�u�ނɂӂ��킵��������v��K�v�Ƃ��i�n���L�Q�|�P�W�A�Q�|�Q�O�j�A�ِ��Ƌ��͂��ĐV���ȋ�������o���Ă�����
���ɕ����Â����Ă���i�n���L�Q�|�Q�S�j�B�����āA�L���ɑ����Ă������Ƃ��������ł���Ɖ��߂���A������V����S�����邱�Ƃ͏j��
���ꂽ�̂ł������i�n���L�R�T�|�Q�X�A�o�G�W�v�g�L�Q�O�|�P�Q�A�\���L�T�|�P�U�A���u�L�S�Q�̂P�Q�|�P�V�j(8)�B�@
�܂��A�_�̏j���́A�q��Ɍb�܂�邱�Ƃ���܂���ƍl�����Ă����B�Ⴆ�A�A�u���n���́A�������ȂƑ����̍��Ɍb�܂�Ă������A
�_�ɑ��āu���Ȃ��͉������ɂ�������Ƃ����̂ł����B���͎q�����Ȃ��܂܂ł��v�i�n���L�P�T�|�Q�j�Ɩ₢�����Ă���B�A�u���n���H
���A�j���Ƃ��Ă̐��́A�b�܂ꂽ�V�����܂��Ƃ����邱�Ƃ����ł͂Ȃ��A���̌b�݂��q���ւƈ����p����Ă������ƂŊ��S�ɂȂ�ƍl����
��Ă����̂ł���B
���j
�@�i�P�j�@�O�T�u�\�������̒m�b�v�ł͐l�Ԃ�s���Ƒ�����l���������邪�A�����ɂ����Ă͏n�����v�z�Ƃ��Ă͉��߂ł��Ȃ��B
�@�i�Q�j�@�z�Z�A���P�R�|�P�S�A���҂S�X�|�P�T�B �@
�@�i�R�j�@�_�j�G�����P�Q�|�Q�B
�@�i�S�j�@�֍����O�u�����̎v�z�@�Q�S�̒f�́v�i��g���X�A�P�X�X�W�N�j�̂T�́A�U�͂ɂ����āA�l�Ԃ̑��݂Ɛ����ɂ��Ắu����
�@�@�@�@���v�ɂ��ďڍׂɘ_�����Ă���B
�@�i�T�j�@���r�L�P�V�̂P�O�|�P�S��\���L�P�Q�̂P�R�|�Q�W�ɂ����ẮA�_�͐l�Ԃ������̓���H�ׂ邱�Ƃ��������A���Ɠ��肳��錌��H
�@�@�@�@�ׂ邱�Ƃ��ւ��Ă��邱�Ƃ�A�n���L�X�|�T�ɂ����Ă͐l�ԂƐl�Ԃɂ����镴���ɂ�鐶���̑����͐_�ɂ���ĒNj������Ƃ���
�@�@�@�@���Ƃ́A�_���g�������@�̌��ł���Ƃ������Ƃ��Ӗ����Ă���B
�@�i�U�j�@Abraham J. Heschel, God in Search of Man, �|A Philosophy of Judaism�| (The Noonday Press, Farrer, Straus and
�@�@�@�@Giroux / New York, 1955).�@
�@�i�V�j�@�u�d������Ă��A�m�b���m�����Ȃ��A�{�v�i�R�[�w���X���X�|�P�O�j�A�u�n���̌��A�ÈŁA�A�v�i���є����V�j�A�u�A�{�ɉ���Ƃ������
�@�@�@�@�Ă͂��Ȃ��v�i���u�L�V�|�X�j�Ƃ����@���A����ɂ�����l�Ԃ̎��͋ɂ߂ď��ɓI�ȈӖ������𐬂��Ă���B
�@�i�W�j�@�C�U�����R�W�|�P�O�A���тP�O�Q�̂Q�S�[�Q�T�j�ɂ����Ă͒Z�����Q����Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�����ɂ����鎀���� �Q
�@�E�E�E�V���ɂ��������
�V�����A�����A�u�������_�����̌㔼���ɓo�ꂷ�鎀���ρv����{�I�ȑO��Ƃ��Ă���Ƃ������Ƃ͎��m�̎����ł���B�����A�o
�r�����ߎ��ȍ~�ɂ����āA�u���_�a�v�𒆐S�Ƃ��鋳�c�̐����m�����ꂽ�I���O�T���I����A�I���V�O�N�̐_�a����܂ł̊Ԃ�����
���_�����Ə̂���̂���ʂł���(1)�B���̎����́A�����̌���ƕ����I�ɏd�����鎞���ł���i�I���O�R�[�Q���I�j�B
���̎���ɂ����郆�_�����̎����ς̒��ɂ́A�����ł��Ȃ�p�ɂɈ��p����Ă����ϔO�����@���Ă�����A�t�ɁA����܂Ŏ���
���Ȃ������\�����o�ꂷ�邱�Ƃ�����B�Ⴆ�A�u�l�͎��˂Γy�ɋA��v�i�n���L�R�|�P�X�A���тX�O�|�R�A�P�O�S�|�Q�X�A�P�S�U�|�S�A���u�L
�P�O�|�X�Ȃǁj�Ƃ�������ɂ����Ă͋ɂ߂Ċ�{�I�Ƃ����鎀���ς́A�������_�����ɂ����Ă͂قƂ�Nj�������͂��Ȃ��B���̗��R
�́A����̒����E�w�i���l���Ă������̔@���A�����A���_�������ɗl�X�ȋ������Ă����킯�����A���̂悤�Ȉ��ՂȎ����ς�
�͐l�X�����S���邱�Ƃ͍���ł������̂ł��낤�B
����A�s�ςȊϔO�Ƃ��ẮA�Ñ�I���G���g�I�Ƃ�������m�l�Ԃ͎��˂w����i��݁j�x�֕����v�Ƃ����ϔO�ł���i�w�u���C��ł͉���
��sheol�ƌĂꂽ���A�M���V�A��ɂ�����ɑ�������ϔO�ł���"haid s"�����݂��Ă������Ƃ́A���̊ϔO��s�ω������ő傫��
�������������ɈႢ�Ȃ��j�B�������_�����A�V���ɂ����ẮA���̉���Ƃ����ϔO�́A�P�Ȃ鎀�҂̍��Ƃ����j���A���X�����ł͂�
���A�����ɐ����Ă������ɔƂ����߂���ꏊ�ł���Ƃ������������Ȃ���Ă����i���J�`�P�U�|�Q�R�j�B
����́A�l�X�Ȑ������������l�Ԃ��s���ꏊ�ł��邪�A���ǂ́A�u�Ŋ��̐R���v���邽�߂Ɏb��I�ɑ؍݂���ꏊ�ł���B����
�S�X�|�P�U�A���邢�́A�P�R�X�|�W�ɂ����ẮA�u�_�́A�`�l������ɕ��蓊���Ă����悤�Ȃ��Ƃ͂Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������Ă���A�����ɁA�u��
�̐��̏I���Ɏ��҂͕�������v�Ƃ������߂��݂���B
�َ��^�I���E�̓����ɑ�����ҁA�����Aapocalypticism�i�َ��v�z�j�ɂ́A�P�l�����l���܂߁A���ׂĂ̎��҂��������A�_�ɂ���
���̐R�����Ȃ����Ƃ������߁i���n�l�`�T�̂Q�W�`�Q�X�A�َ��^�Q�O�̂P�Q�`�P�R�j�A���̈���A�P�l�݂̂��������邱�Ƃ��ł��A�i����
������������Ƃ������߂�����i�\�������̎��тR�|�P�Q�A���J�`�P�S�|�P�S�Ȃǁj�B�@
����̃_�j�G�����P�Q�͂̂Q�|�R�ɂ����Ă��Ŋ��̐R���ɂ��ĐG����Ă��邱�Ƃ��琄�@�ł���悤�ɁA����E�V��ɂ�����l�Ԃ�
�u���v�Ɓu���v�́A�_�ɑ��鉞���Ƃ��đ����邱�Ƃ��ł���B�V��ɂ����鎀���ς����������ōł��d�v�Ȃ��̂́A�u�C�G�X�E�L���X�g
�̕����v�ł���B�����ƂƂ��ď��Y���ꂽ�C�G�X�́A�����Ƃ��Ă͍ł��c���ȁu�\���ˁv�Ƃ������@�ł��̖���D��ꂽ�B�����A�C�G�X
�قǐ_�̈������H�����҂͂��Ȃ������ɂ�������炸�A���̍Ŋ����\���˂ɂ�鏈�Y�Ƃ��������́A�����̒�q�������]�̂ǂ���
�˂����Ƃ���(2)�B�C�G�X���������ꂽ��A�C�G�X�̎��̂���ꂩ������Ă��܂����Ɠ`�����Ă��邪�A���̂��Ƃ��A�C�G�X�̒�q����
�ɂ�����X�Ȃ�s���������A�����ɁA��̐��E�ɓ˂����Ƃ����ƂɂȂ�i�}���R�`�P�U�̂P�|�W�A�}�^�C�`�Q�W�̂P�P�|�P�T�A���n�l�`
�Q�O�[�P�R�j�B
���̂悤�ȏ̉��A�y�g���ƃ}�����i�}�O�_���̏��j�ɁA�h�ٕρh�Ƃ������ׂ����Ԃ��N�����B�C�G�X�����Y����A�ނ�́u���v�ւ̓W�]
�͂��Ƃ��Ƃ����Ă��܂����킯�ł��邪�A�ނ�́A����܂ŐM���Ă������Ƃ͑S���ʂ̎����̖���F������Ɏ������̂��B�����
��̉����Ƃ����ƁA�����܂ł��Ȃ��A�u���͂��̃C�G�X���Ăь��ꂽ�v�Ƃ������Ƃ��i���R�����g�P�T�̂T�`�V�j�B�C�G�X�̎��̂����
��������������Ƃ��������́A�u�C�G�X�͐_�ɂ���ĕ���������ꂽ�v�Ƃ������߂������A�u�_�́A�C�G�X�����l�����̒�����N����
���v�Ƃ����\���i���}���U�|�S�A�P�O�|�X�A�g�r�s�`�Q�|�Q�S�A�R�|�P�T�A�T�|�R�O�Ȃǁj�B����́A��ɁA�u�L���X�g�͖����Ă���҂���
�̏���Ƃ��āA���҂����̒�����N�����ꂽ�v�i���R�����g�P�T�|�Q�O�j�Ƃ����\���ɕς��A�����ɁA�C�G�X�̕����ɂ�����َ��v�z��
���ۂ��n�܂�B
�t�@���T�C�h�̃��_���l�ł���p�E���́A�I���R�R�N���A�_�}�X�N�X�ߍx�ŁA�˔@�A�C�G�X�ɏo��Ƃ����_��̌��ɑ��������i�K���e��
���P�|�P�U�A�g�r�s�`�X�̂P�|�X�j�B�p�E���́A������_�@�Ƃ��āA���n�L���X�g���̓`���ɗ͂����n�߂��B����́A�p�E���̎莆�́A
�h���n�L���X�g����Ɋւ���`����̕�Ɂh�Ƒ�������悤�ɂȂ����B
�p�E�����W�J�����_�w�́A�����܂ł��Ȃ��u�\���˂̐_�w�v�ł���B�\���ˌY�́A���[�}�鍑�ɔ�������҂ɑ��錩�����߂Ƃ��Ă̎E
�Q���@�ł���A�ɂ߂Ďc�s�ŕ��J�̋ɂ݂Ƃ���Ă������Y�@�ł���B�C�G�X�����Y���ꂽ��A�N��l�Ƃ��ď\���˂ɂ��Č��y����
���Ƃ͂Ȃ��������A�p�E���͏��߂āA�\���˂��A�M�̏ے��Ƃ��Ă��̑b��z�����̂��B
�p�E���́A�u��O�`�����s�v�i�g�r�s�`�P�W�|�Q�R�`�Q�P�|�P�S�j�ŏ������u�R�����g�l�ւ̑��̎莆�v�ɂ����āA�ɂ߂Ė��m�ɁA�u���t��
�m�b�v�i�P�|�P�V�j�ƑΔ䂳���A�u�\���˂̒m�b�v�i�P�|�P�W�j������Ă���B�����̐l�X�ɂƂ��ẮA�\���˂ɂ��ĐG��邱�Ƃ́A�܂���
�h���̍������̂��́h�ł���ƍl�����Ă����킯�ł��邪�A�p�E���́A�\���˂��u�_�̒m�b�v�ł���Ɩ��������̂��i�P�[�P�W�A�Q�P�`
�Q�S�j�B�������ŁA���̂��Ƃ�ُؖ@�I�ɏq�ׂ�Ȃ�A�u���E���E�V���v�Ƃ����v���Z�X�ɂ����āA�Ƃ�킯�u���v�ɏd�_��u�����Ƃɂ���āA
�u�V���v�A�܂�A�h���������h�Ƃ������̐��ڂ�N���ɏq�ׂĂ���Ƃ������Ƃ��킩��B
���̌�A�I���V�O�N��A�p�E���́A���ُؖ̕@��傫���W�J�B�X�O�N��ɂ����ẮA��l�������ŁA�����ُؖ@�́u���E���E�V���v��
�ꌳ����}��B����ɂ���āA�C�G�X�̎��́u�V���v���܂��A����́A�h�V�����̂��́h�ƂȂ�B����͂܂�A�C�G�X���\���˂ɂ�����
���Ƃ������Ƃ��A�u�C�G�X���V�ɂ�������v�Ƃ������ƂƓ����l���Ƃ��đ����Ă��邱�Ƃ��Ӗ�������̂��i�R�|�P�S�A�W�|�Q�W�A�P�Q�[�R�Q�`
�R�S�j�B�����āA�܂��ɁA�\���˂̃C�G�X�́A���𐂂�đ����������Ƃ��A�u����������ꂽ�v�Əq�ׂ��i�P�X�|�R�O�j�B
���j
�@�i�P�j�@���_�����́A��ɁA�u���r�I���_�����v�ƌď̂����悤�ɂȂ�B
�@�i�Q�j�@�j�̒���q�����́A�\���˂�ʑO�ɂ��ăp�j�b�N��ԂɊׂ����i�}���R�`�P�S�|�T�O�j�B
|

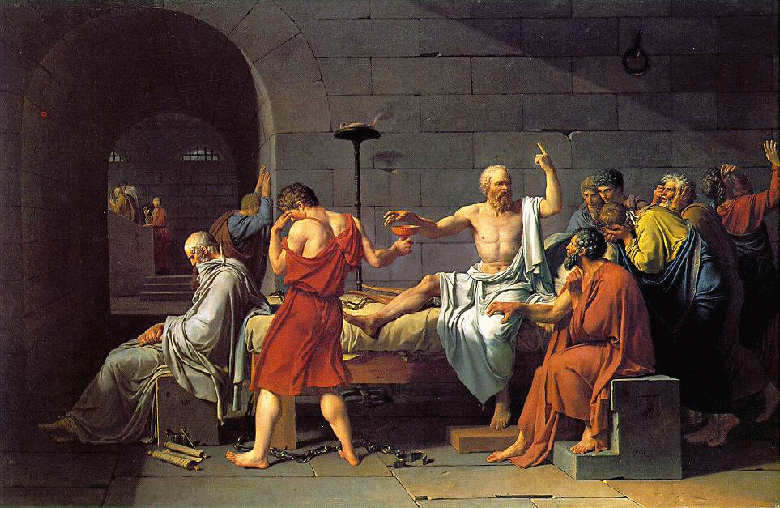

 �E
�E










